どうも、31等星です。
今回は、研究室一期生の僕がこれまで大学院生活を送ってきて思ったことを書きたいと思います。本記事ではこのブログの名前の通り、日常を書いてみます。
これから研究室を選ぶという方には少しだけ参考になる内容かもしれませんが、基本的には本記事は雑談やエッセイに近い内容です(研究室選びに関する情報を得たい人は、研究室の選び方に関する過去記事も読んでみてください)。

僕は研究室配属の時に新任で弊大学に来た先生の研究室に入ったので先輩が1人もいません。配属当時は先輩がいないし自由で良さそうだなぁと思っていました。
しかし、年次を重ねて後輩が増えるにつれて「後輩たちの方がより良い環境で研究できてるんじゃない?やっぱり研究室には先輩がいる方が良いんじゃない??」と思うようになったので、本記事ではそれに関するお話を書いてみます。
ブログ記事のタイトルでは「苦悩」と言っていますが、苦悩と言うよりは単純に「後輩たちを見ていると僕の頃にはなかったものが色々あって羨ましいなぁと時々感じる」というのが今回のお話の趣旨です。
以下には、研究室一期生だった僕になかったものを4つと、それに対して思ったこと書き綴ってみます。
ロールモデルがない(マイルストーンがない)
僕には研究室に先輩がいないので、自分の研究分野でいつの時期にどれくらい研究の進捗があれば及第点なのかがわかりませんでした(と言うか今でもわかっていません)。
ロールモデルを見つけるために、指導教員を含め自分の分野で業界に生き残っている研究者の方々の学生時代の業績をいろいろ見てみましたが、すごすぎてあまり参考になりませんでした。
このことは、研究者になるにはそれくらい学生時代に業績を残せるほど優秀でなければならないことを示唆しているような気がしますが、もう少し身近で手頃なロールモデルがあればより博士課程を生きやすかっただろうなぁと感じます。

一方で僕の研究室の後輩たちは手頃なロールモデルとして僕という先輩を参考にできるので、とりあえず当時の僕を越えれば及第点と思えるのは羨ましいところですね。
しかも僕は大した学生じゃないので僕を追い抜くのは割と簡単で、手軽に満足感を得るためのマイルストーンとなっているのは後輩たちにとっては良い点なのではないでしょうか(多分)。僕の後輩たちにはぜひとも僕が大した学生でないことに感謝してほしいところです。
あらゆるもののフォーマットがない
僕は研究室の一期生だったので、あらゆるフォーマットがありませんでした。例えば、
- 修論・論文
- 学振の申請書
- 学内RAの申請書
- 学会発表のスライド・ポスター
などです。
もちろん以上の中には指導教員や他研究室の先輩から頂いて参考にしたものもありましたが、指導教員の頃のものは時代が違っていて少し参考にしづらい部分があったり、他研究室の先輩のものは分野が違っていて内容に関して真似られる部分が少なかったりしました。
というわけで上記のようなものを作る時に僕は毎回自分でオリジナルのものを生み出さなければならなかったので、その点は少し大変だったように感じています。
後輩たちはみんな僕が作成したフォーマットを参考にしながらさらにそれを自分流に改良していくことができるので、より完成度の高いものを作れるのが良いなぁと思います。
そのようなフォーマットは代を経るごとにどんどん洗練されていくものなので、より下の方の代の後輩たちは良いお手本を参考にすることができて羨ましいところですね。
細かいことを聞ける相手がいない
先輩がいないことのデメリットとして、わざわざ指導教員に聞きに行くほどではない(と思える)些細なことを聞く相手がいないことがあると感じました。
例えば僕の場合、基礎的な物理学の勉強やプログラミングの上手な書き方などを時々人に聞きたくなります。
誰かに聞けば10分もかからず解決するようなことでも自分で調べると数時間以上かかるということもよくあるので、気軽に質問できる人が周囲にいることは研究を効率良く進めるために重要だなぁと思います。

幸い、僕が修士の学生だった頃に博士の留学生が弊研究室に入ってきたので、その先輩(学年としては先輩だけど研究室歴としては僕の方が長いので同級生みたいな間柄でした)に些細なことを聞くことができました。
しかし、英語で喋らないといけないので細かいことを聞きづらいのは難点です(もっと英語力を上げたいところ)。博士論文はその留学生のフォーマットを参考にできるので少しラクをできて嬉しいですね。
しっかりした教育体制がない
例えば、僕が研究室に入った頃には研究室では教科書の輪読ゼミなかったのですが、三期生が入った頃あたりから教科書の輪読ゼミが研究室で行われるようになっていました。
他にも、僕が研究室に入った頃の論文紹介はテキトーに論文を紹介するだけの緩い会だったのですが、年を経るごとにフォーマルなものになってプレゼン力をしっかり鍛えられる会に変わっていっていました。後輩たちの方がしっかり学ぶことができて羨ましいところです。

ちなみに僕の指導教員の名誉のために言っておきたいのですが、これはあくまでも時代を経るごとに「ベター」になっていっただけであって、元の教育体制が悪かったというわけでは決してありません。
実際、僕の指導教員はとても教育力がある方で、僕が研究室に配属された頃からしっかりと教育をしてくださっていました。
ただ単に、最近の方が昔に比べて、指導教員がよりちゃんと学生のレベル感を把握していてより良い指導をしているなぁと思うということです。
所感・まとめ
ここまでいろいろ「なかったもの」を書き連ねてきましたが、それはそれで良かったのかもしれません。
参考にするロールモデルもフォーマットもない状態で手探りで進んでいくのは大変ですが、冒険みたいで面白いのかなぁとも思いました。
また、ゼロから自分で調べたり考えたりする時間が長かったおかげで自力で学ぶ力が身についたとも思います(多分)。
それに、自身が最初に作ったフォーマットが後輩に代々受け継がれていくと思うと何となくちょっとだけ誇らしいような気もします。ヒロアカのワンフォーオールみたいですね。
結局僕は研究室一期生以外の人生を生きたことがないので、何がベストだったのかは未来永劫わからないところではありますが。N=1。
そういえばこんな投稿があったことを思い出しました。研究室一期生であることで道に詳しくなれたんでしょうか。
というわけで本記事では、研究室一期生の僕のぼやきを綴ってみました。似たような境遇の方々に共感してもらえたら嬉しいです。今回はこんな感じで。
それではまた次の記事でお会いしましょう。



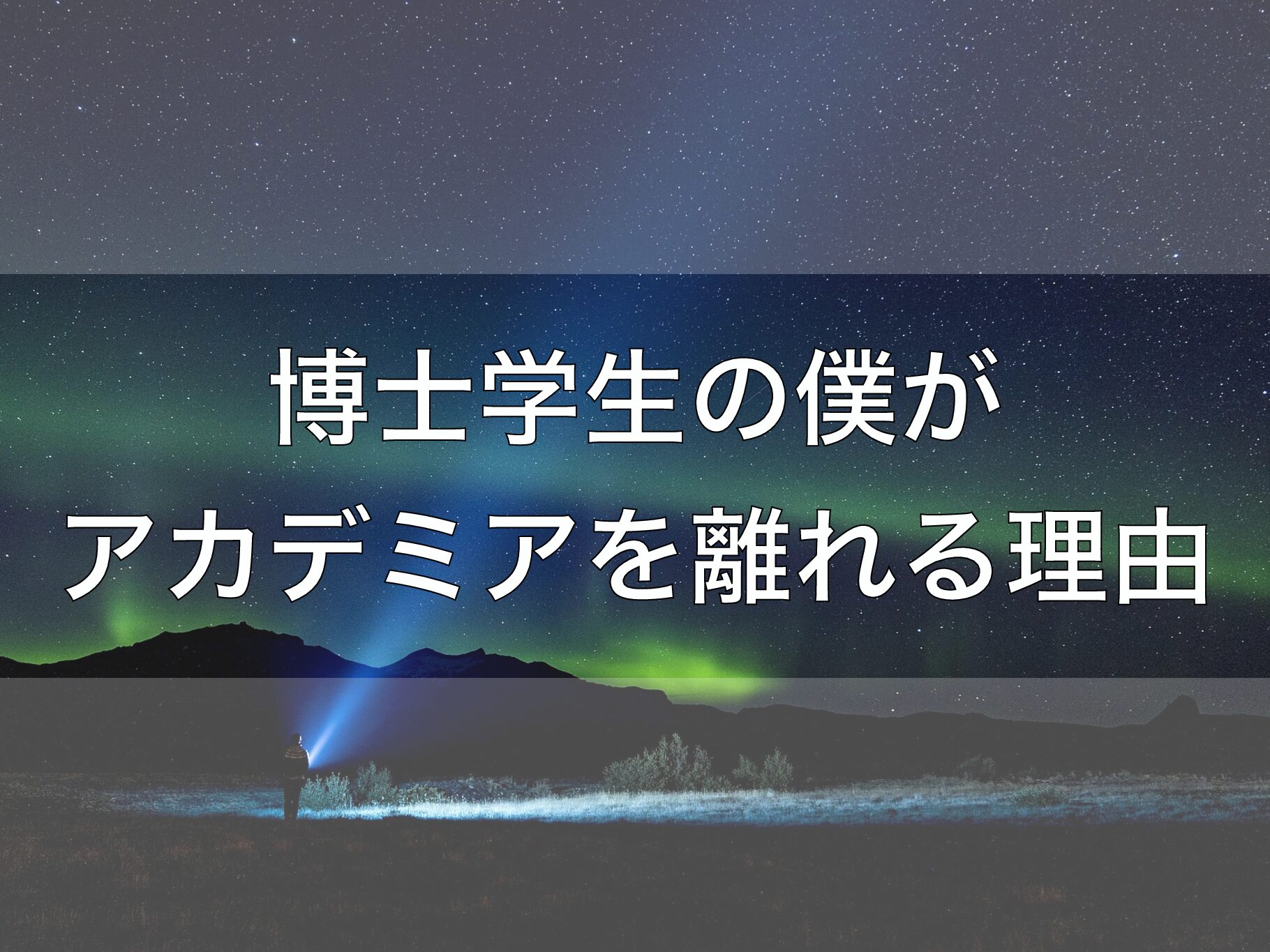
コメント