はじめまして。国立大学の博士後期課程に所属している31等星です。
今回は、大学院進学を考えている学部生の方向けに、大学院生活を楽しく幸せに過ごすための研究室・指導教員の選び方を紹介します。
結論から先に言うと、指導教員の人柄・指導力・研究力・金銭的裕福さを見ることが大事です。
僕は運よく研究室選びに成功したおかげで、大学院に入ってからそれなりの成果を上げることができました。
修士2年間で研究発表賞を3回もらったり、査読付き海外雑誌に論文が受理されたり、学振特別研究員に採用されたり、奨学金返済免除に推薦してもらったり、などなど。
学部生時代に学科で下から2番目の成績だった僕(ポンコツ)からは想像できないくらいには成長できたと思っています。
僕の努力・能力だけではこれらの業績を収めることは絶対にできていませんでした。上記の結果は間違いなく今の研究室・指導教員のサポートのおかげです。
実りのある大学院生活を送るには、研究室・指導教員選びが全てと言っても過言ではありません。
研究室というのは「小さな社会」です。
大学院生活で2年間ないし5年間一緒に過ごすことになる「直属の上司(指導教員)」は慎重に選びましょう。
しっかりとリサーチして、自身が最大限成長できそうな研究室を選べると良いですね。

以下では、修士課程・博士課程で研究生活を送ってきた僕が「過去に戻って研究室・指導教員を選ぶなら何を基準にするか」を書いていきます。
…とその前に、
ほとんどの人がやってしまいがちな間違った研究室の選び方を紹介します。
それは研究テーマで研究室を選ぶことです。
多くの学部生は自分がなんとなく興味のあるテーマで研究室を選んでしまいがちだと思いますが、研究テーマ(だけ)で選ぶのは最も愚策だと思っています。
というのも、学部生のもつ知識だけではどんな研究が自分に向いているか・自分はどんな研究を本当におもしろいと思うのかが判断できないからです。
個人的には、その分野が好きな人なら多分どの専門を選んでもそれなりに楽しめるんじゃないかなぁと思っています。
それに研究しているうちに少しずつ興味も変わってくるので、研究テーマなんてテキトーに選んじゃっても問題ありません。
「どうしてもこの研究がやりたくて仕方ないんだ!俺はこのテーマで第一線を行く研究者になるんだ!!」という鋼よりも強い意志がある人以外は、研究テーマだけで研究室・指導教官を選んでしまわないように気をつけましょう。
この主張と似たことを言っているのが以下のSNSの投稿で、これは研究者になりたい人向けの話ですが、論文が出やすいテーマを選ぶのは研究者を目指さない人にもオススメです。というのも、論文が出やすいなテーマだと在学中の短期間で「1つの研究をやり遂げる」という研究者の仕事を一通り体験することができるからです。
また「研究テーマはあまり重要じゃない」という由はこちらの方も言っています。
さて、それではこれから研究室・指導教員の選び方について書いていきます。
人柄
まずは人柄からです。
研究室・指導教官を選ぶための4項目を挙げましたが、その中でも一番大事なのは指導教員の人柄だと思っています。
先ほども書きましたが、研究室というのは「小さな社会」です。
そこでは「指導教員と一緒に」研究をします。
もし指導教員と性格が合わなかったら研究が苦痛になってしまうので、まずは人柄を見ましょう。
ものの言い方がキツくないかとか、研究室がブラックすぎて大学に来なくなった先輩がいないかとか、そういうところもリサーチしておくと良いですね。
必ずしも優しい人が良いというわけではありませんが、少なくとも一緒にいてネガティブな気分にならない程度に相性の良さそうな人を指導教員として選ぶと良いと思います。
良い研究は良い人間関係から。
指導力
続いては指導力です。
大学の先生の指導力を見定めるには、その研究室に所属している修士・博士の学生がどれくらい成果を上げているかを見ましょう。
- 論文を出しているか
- 研究発表賞などを受賞しているか
などを見ると良いです。
所属している先輩の名前で論文検索してみるとか、実際に先輩方に直接聞いてみるとか。
特に博士課程に進学予定の人は修士1年の間に業績を上げていると学振DC1(修士2年の5月に申請)でかなり有利になるので、先輩方が早い段階で成果を出しているどうかを確認しておくと良いでしょう。
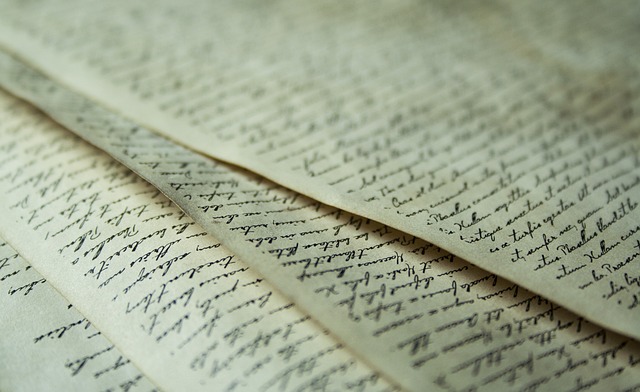
あとは、「研究」以外の部分も指導してもらえるかっていうのもめちゃめちゃ大事だと思っています。
研究にはいろんな能力が必要で、どの部分をどの程度指導してくれるかは研究室によって大きく異なります。
多くの人がまず最初に挙げそうな「研究」に必要な能力はほとんどの研究室でる程度ちゃんと指導してもらえているイメージがあります。
- 科学の知識
- 問題解決能力
- 論理的思考力
のあたりですね。
でも、研究にはこれら以外にも重要な能力がたくさんあって、そういう部分まで指導してもらえる研究室は数少ないです。
必要な能力というのは例えば、
- 論文・学会の予稿・学振などの申請書を書くための文章力
- 学会・ゼミなどでわかりやすい発表をするための説明力
などです。(他にも英語力・リーダーシップ・デザイン力とか挙げればキリがないので、特に個人的に重要だと思う2つを書いておきました。今度機会があったら研究に必要な能力についての記事を書いてみようかな。)
このあたりは、研究室・指導教員によってどの程度指導してもらえるかがかなり異なっている印象です。(僕の同期には指導教員に学振の書類を見てもらえない人もいます。。。)
こういう部分を指導してもらえている学生とそうでない学生では、修論発表や修士論文のクオリティが全然違っていました。
特に修士で卒業する予定の人・研究職を目指すわけじゃない人にとっては、研究で得た科学的な知識そのものよりも研究を通して身につけたポータブルスキルの方が会社に入ってから重要になりますます。
なので、こういう部分を指導してくれる人を選ぶと将来役に立ちそうです。
このへんは研究室に所属している先輩に聞く以外にないのでしっかり確認しておきましょう。

また、「自分自身がどれくらい指導されたいか」と「指導教員がどれくらい熱心に指導するか」がマッチしているのも割と大事だと思います。
先生によって、放任主義だったり過干渉だったり本当に様々です。
もしあなたが放置されすぎると怠けてしまうタイプならある程度いろいろ言ってくれる指導者の方が良いでしょうし、干渉されるとやる気がなくなるタイプなら放っておいてくれる指導教員を選ぶ、など自分の性格・ペースに合った人を選ぶと良いと思います。
ちなみに僕の指導教員は放任主義でもなく過干渉でもなく、基本的には怠け者の僕の尻を良い塩梅に叩いてくれてとてもありがたいです。(博士課程学生なんだから何も言われずともちゃんと進捗を生まなければ。。。)
研究力
続いて指導教員の研究力です。
大学院は研究をするところなので、良い研究をするために研究力のある人から指導してもらいましょう。
研究力を見るには、その先生がちゃんと業績を上げているかどうかを見るのが手っ取り早いです。
大学の先生の名前(+大学名とか)でググるとウェブサイトが出てくるので、そこから出版された論文リストを見ましょう。
数年以内に論文を出しているか、これまでの論文がどれくらい引用されているかなどがチェックポイントです。
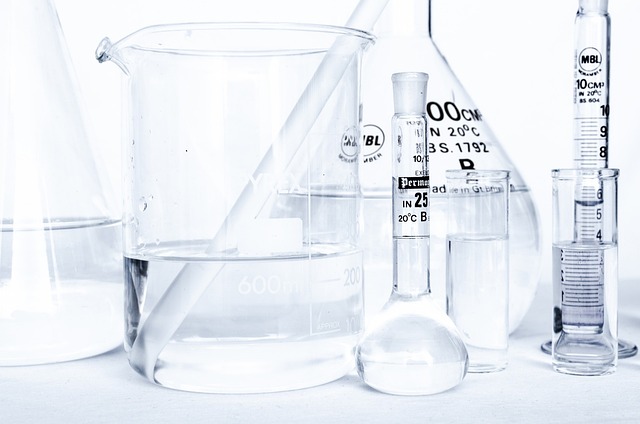
個人的な意見ですが、「研究力」というのは「自分の力量で解けそうなレベルで、かつ世界中の誰もが気づいていない面白い問題を見つける力」だと思っています。
そもそも研究という行為は「未解決問題を解決すること」です。
僕らが中学生や高校生(や学部生)の頃に思い描いていた「夢のある研究」はすでに誰かが発見した「知識」なので、残念ながら研究テーマにはなりません。
研究というのは基本的には、その分野での「些細な未解決問題」を解決することの積み重ねです。(「一部の天才が大発見をする」みたいなのはごく限られた分野だけの話です。)
研究を進める過程では、泥臭い実験やプログラミングを一生懸命するわけですが、そういう作業は正直誰でもできてしまいます。
なので、問題を解決する能力よりも問題を発見する能力が研究では重要です。
つまり、研究力というのは「自分の力量で解けそうなレベルで、かつ世界中の誰もが気づいていない面白い問題を見つける力」であると言えると思います。
この「研究力」がある人たちが論文を量産しているイメージです。

「研究力」のある人に指導してもらえると、初めての研究がすごく楽しくなります。
最初の研究では自分だけで研究テーマを決めるのは難しいので、指導教員から研究のアイデアをもらうことがほとんどだと思います。
なので、学生にできる難易度でかつちゃんと成果の出る研究テーマを一緒に考えてくれる指導教員を見つけましょう。
もし最初の研究が頑張っても成果の出ないテーマだったら面白くないので。
それに、研究を始めて早い段階で結果が出ているといろいろなメリットがあります。
例えば、
- 修士で就職するにしても学生の間に「研究者の仕事」を一通り体験できる
- 博士進学希望の場合、論文が出版されていると学振DC1で大きなアドバンテージになる
- 論文があると奨学金が返済免除になりやすい
などです。
というわけで、研究力のある指導教員を選びましょう。
金銭的裕福さ
最後は指導教員の金銭的な裕福さです。
これは、その先生がどれくらい科研費を持っているかということです。
予算が潤沢な研究室だと研究に必要なもの/ことは科研費から出してもらえます。
- ノートパソコン
- キーボード
- ディスプレイ
- 出張
などです。
これらのものを自分で用意するとなると貧乏な学生にとってはかなりの負担なので、科研費をたくさんもらっている先生を選びましょう。(ただし、科研費をたくさんもっていても学生のためには使ってくれないケチな人もいるらしいので注意が必要です。)
こういう部分も先輩に聞いておきましょう。

大学の先生がどれだけ科研費をもらっているかは、こちらのウェブサイトから確認できます。
ここに教員の名前を入れると、その教員が現在どれくらいの科研費をもらっているかがわかります。
ついでに、今もらっている科研費だけでなくこれまでにどれくらい科研費に採択されたかも見ておくと良いでしょう。
というのは、科研費に採択されるほど申請書の書き方が上手い・業績があるということの判断にも使えるからです。
教員の科研費の状況も忘れずに確認しておきましょう。
以下の投稿で言われているように、研究室ごとに差があるのは不平等で、改善されるべきシステムだとは思います。ただ現状はそうなっていないので、今のところは自身が損しないように立ち回るしかありませんね…
まとめ
研究室生活を楽しく過ごすための指導教員選びのポイントは
- 人柄
- 指導力
- 研究力
- 金銭的裕福さ
の4つでした。
2年間または5年間の人生を決める大事な選択ですので、じっくり考えて研究室・指導教員を選んでください!
修士で大学を離れる人も、博士まで残りたいという人にもこの記事が参考になれば幸いです。
もちろん上記の4つだけが全てではないと思うので、ぜひいろいろな人の話を聞いてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
これから大学院生活で役に立ちそうな記事を書いていく予定ですので、応援よろしくお願いします。
SNSなどでシェアしていただけると泣いて喜びます。
それでは良い研究室ライフを!

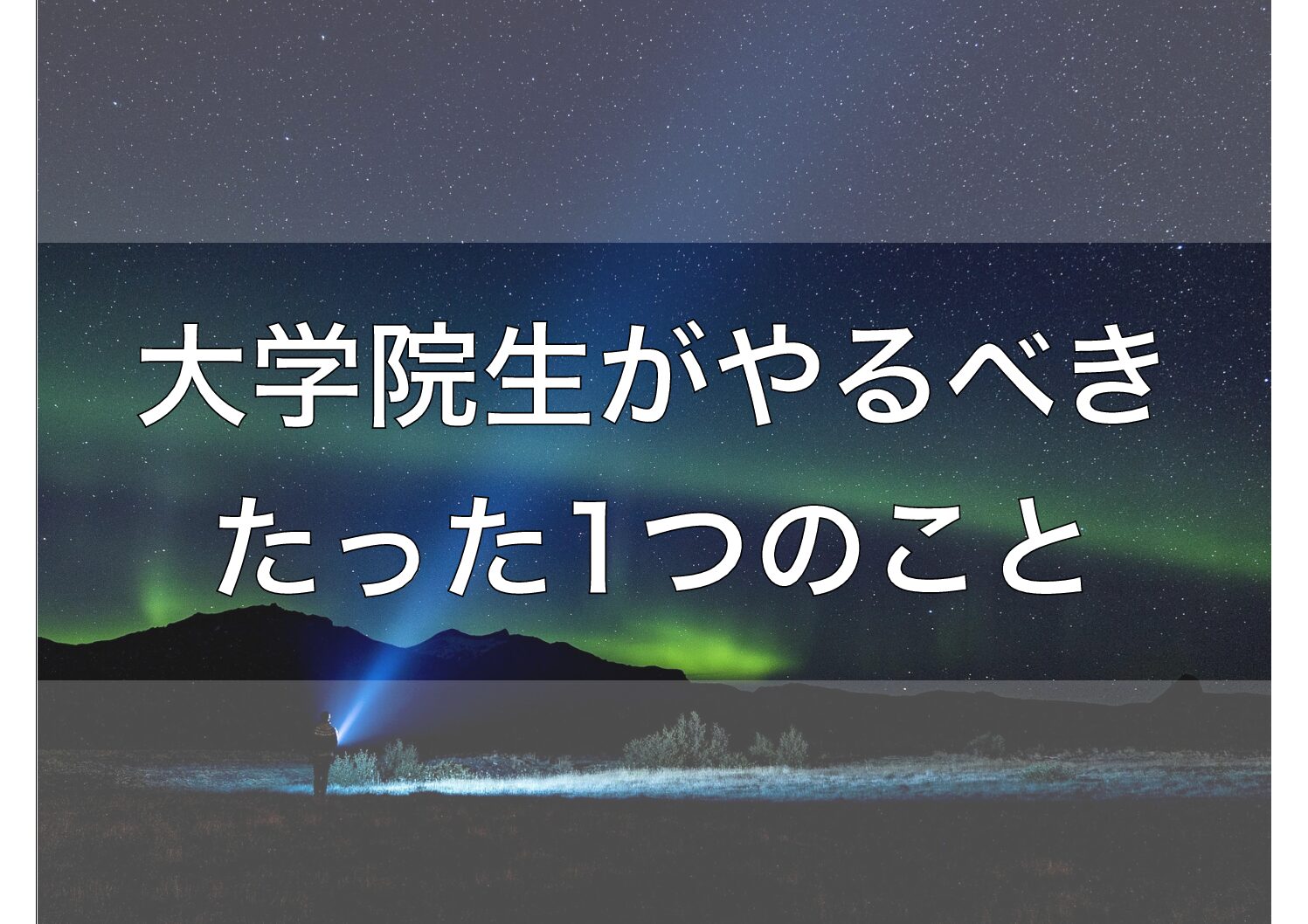
コメント