どうも、31等星です。
今回は博士課程まで進んだ僕が、アカデミアを離れる決断をした理由についてお話しします。アカデミアにいる人たちが将来の進路を決める参考になれば幸いです。
(僕の就活事情については以下の記事をご覧ください。)
アカデミアを離れる理由を話す前にまずは博士課程に進学することを決断した理由を簡単に書きたいと思います。
元々研究者という職業にぼんやりと憧れがあったので大学入学時から博士課程進学を視野に入れていました。
その上で、修士課程の間に博士課程進学を決断した理由(と括弧内は実際に進学した後の実情)が以下です。
- 研究を通して新しいことを知るのが楽しいと思った
(今でもそう思う) - 国内外の出張でいろんな経験ができるのが楽しいと思った
(今でもそう思う) - 時間的に自由だと思った
(部分的にはそう、部分的に違う) - 自由で好きな研究ができると思った
(部分的にはそう、部分的に違う) - 自分ならアカデミアで生き残れると思った
(勘違いだった)
などと、割と博士課程に進む人たちではスタンダードな理由かと思います。
それではこれから「博士課程まで進んだのにアカデミアに残らない理由」を書きたいと思います。
大雑把には「自分はアカデミアに向いていないと思ったから」なのですが、以下に詳細を書いていきます。
以下の理由の並び順は、僕のアカデミアを離れる決意に大きな影響を与えたと思う順番になっています。
ちなみに以下の文章はややネガティブに聞こえるかもしれませんが、基本的にはフラットに向き不向きの話をしているだけであるということにご留意ください。アカデミアが良い悪いの話ではありません!
自身の能力が足りない
ただひたすらシンプルに、自身の研究能力ではアカデミアで職を得ることができないと思ったのがアカデミアを離れることにした1番の理由です。
自分よりも優秀な人たちを見ていると、僕って大したことないよなって日々思ってしまいます。
僕の能力は博士学生の中でめちゃめちゃ低いわけではないとは思いますが(自己評価は総合的に見て「中の下〜中」あたり)、パーマネントのポストに就けるのは博士号を取った人の中で「上」の部類にいないといけないはずだと思うと全然能力が足りないので、アカデミアでは生きていけないと思うに至りました。
能力がある人でも運が良くないとなかなかパーマネントポストを得ることができないこの世界で、凡庸の僕が生きていくのは厳しそうですね…

ポスドクをやってから就職するというのもナシではないと考えていた時期も少しありましたが、ポスドクまで行ってしまうと就職の選択肢がかなり狭まってしまいそうだと思ったので、ギリギリ新卒カードを使える博士卒のタイミングでアカデミアの世界から脱出することを決意しました。

ちなみに、博士課程在学中に「自分の能力が足りない」と感じたのにもかかわらず修士課程の頃に「自分ならアカデミアで生き残れる」と勘違いしていたのは、修士1年生の頃に学会で2回優秀発表賞をもらっていたからです。
「こんなに学会で受賞しているんだから自分こそが研究者になる器を持った人間なんだ!」と勘違いしていました。青臭くてかわいいですね。
学会発表が上手いことと研究者として優秀であることは必ずしも一致しないということを理解していなかった自分が懐かしいです。
自身の熱意が足りない
わざわざ研究するためだけに遥々海外からやってきた留学生や、呼吸するように研究をし続ける指導教員や後輩などを見ていると、自分の研究に対する熱意が足りないと思うようになったのも大きな理由の1つです。
土日も含めて毎日楽しそうに12時間くらい研究している彼らを見て「叶わないなぁ」と思ってしまいました。
僕もそれなりに研究が好きだから博士課程に進学したわけですが、僕は週に6回10時間程度働くだけでだいぶ頑張ったなぁと感じてしまいます。
この程度の労働時間で「頑張った」と思ってしまう時点で、僕は圧倒的に熱量が足りていないんですよね。
「毎日12時間くらい働いても苦だと思わないくらい研究に打ち込めること」こそが研究者としての素質なんだと僕は思います。
そういった意味で僕は研究者としての素質がないんだと感じました。
以下の投稿がものすごく同意できます。
こちらの方の投稿も。
研究の律速段階となる作業が好きじゃない
研究において律速段階(全行程の中で最も時間がかかるパート)となるのが僕の研究分野の場合はプログラミングだったのですが、僕はプログラムを書くことをあんまり好きになれなかったというのも大きな理由です。
僕も「研究」は好きでしたがそれは単に「その研究テーマが好き」なだけであって、「研究のために行う行為(分野によっては実験・プログラミング・フィールドワークなど)が好き」なわけではなかったということに気づいてしまいました。
「研究テーマが好きであること」は研究者として重要な素質であることは間違いないですが、それよりも「研究のために行う行為が好き」の方が研究者の素質として重要だと僕は思います。
就活生がよく読む本『苦しかった時の話をしようか』にも将来の仕事を考える際には「何を『する』のが好きか?という動詞で考えるのが大事」と語られていたので、これは重要なポイントだと思います。
結局研究をしている中で最も時間を費やすプロセスを楽しめないと研究に没頭することができないんですよね。
研究に没頭するためにも「研究が好き」を上記のようにちゃんと分解して考えるのが大事だと痛感しました。
僕もプログラミングが好きだったら頑張らずに毎日12時間とか研究できたのかなぁ。
自身の得意をアカデミアで生かせない
僕がこれまで研究生活を送ってきた中で他人より上手にできると感じたことが学会発表(もう少し一般的に言うなら、難しいことを人にわかりやすく説明すること)だったのですが、このプレゼン力はアカデミアではそんなに重要視されないと思ったということもアカデミアを離れる理由の1つです。
研究者の至上命題は研究成果を生み出してそれを論文として出版することなので、上手なプレゼンをすることは「必要」ではありません。
もちろんプレゼンが上手いに越したことはありませんが、プレゼンがそんなに上手くなくても研究者として生き残っている人はたくさんいますよね(実際、学会に参加すると少なくない数の人が聞くに堪えないプレゼンをしているのを見かけます)。
せっかくプレゼンが上手くてもそれを生かせないのは宝の持ち腐れなんじゃないかと思って、アカデミアじゃない業界に行った方が自分自身が幸せになれそうと考えるようになりました。
ちなみに、僕がプレゼン時に気をつけていることを綴った記事がこちら。ぜひ読んでみてください!
自分自身が最先端である必要がない
僕自身が最先端の知識の開拓者である必要はないのではないかと思うようになったというのもアカデミアを離れる理由の1つです。
研究をするということはこの世界でまだ解決されていない問題に取り組むということで、最先端の知識を自分の手で開拓するプロセスはものすごくエキサイティングだと思います。
その最先端の知識を発見した瞬間の「今この事実を知っているのは世界で自分だけ」という優越感のようなものが気持ち良いというのも分かります。
ですが、僕は誰かの書いた論文を読んで新しい知識を入手するだけでも満足できるということにいつの日にか気づいていました。
誰かが発見した知識をお裾分けしてもらうだけでも十分面白いと感じられるんですよね。
むしろ自分の手で最先端の知識を開拓する時間があるならその時間で既存の知識を学ぶ方が効率良く楽しめると思ったので、自分は研究者には向いていないと考えるに至りました。
思っていたほど自由じゃない
研究者であるということが、思ったよりも自由じゃないと感じ始めたというのも理由の1つです。
修士・博士の学生も含め研究者であれば自由に好きなことをやれるというイメージがありましたが、必ずしもそうじゃないということにいつしか気づいてしまいました。
例えば研究テーマに関しても、完全に自由に選べるわけではありません。
もし学生であれば学位の取得のために研究内容は「学生の間の短いスパンで結果が出そうなこと」を選ぶ必要があります。
研究者として生き残りたいのであれば「将来的にその分野で重要になる課題」を選ばなければなりません。
また、どんなに楽しい内容の研究に取り組んでいてもどうしても退屈な作業に出会います(人によっては科研費などの申請書の作成、メールを書く、学会発表をする、ゼミの準備とか諸々)。
アカデミアで研究者として研究をしようが民間企業で会社員として働こうが生きている限りどうしてもやりたくないことに出会うもので、それがお金を稼いで生活するということなんだなぁと最近は思います。
もし本当に自由になりたいなら一昔前に流行ったFIRE(Financial Independent, Retire Early:経済的に自立して早期退職するやつ)をしなければいけませんね。

というわけで、研究者は自由を手に入れるために目指すものではないと思いました(研究者になるまでの過程はものすごく大変ですし)。
もちろん世の中にある多くの職業に比べて研究者という職業の自由度が高いことは間違いありません。
実際、今でも僕は博士課程の学生としてフレックスタイムで好きな時に好きなだけ研究ができるのは良い点だと感じています。
まとめ
というわけで今回は、博士課程の僕がアカデミアを離れる決断をした理由についてでした。
繰り返しになりますが、この記事は研究者という職業がこの僕31等星にとって適職ではなかったという話であってアカデミアが良い悪いを語るものではありません。
むしろ僕は多くの人が博士課程に進学して学問を発展させていってもらいたいと思っています。
ただ、研究者という職業はパーマネントポストに就くまでの道のりがものすごく大変なので、進路を決める時には自分自身の適性をよく考えた上で判断していただきたいです。
その判断材料として本記事が少しでも参考になれば幸いです。
そういえば以下の本『アカデミアを離れてみたら』が面白かったです。アカデミア以外で活躍している博士号持ちの方々の人生がたくさん綴られています。興味があればぜひこちらも読んでみてください。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
追記:本記事を自分で読み直して思ったこと。元々アカデミアを離れる決意をした最初の理由が「自身の能力が足りない」で、残り5つの理由は「アカデミアを離れる決意を自身に刷り込ませるために後から言語化した」というのが真実に近い気がしました。どの理由も元々うっすらとは感じていたのは事実ですが。
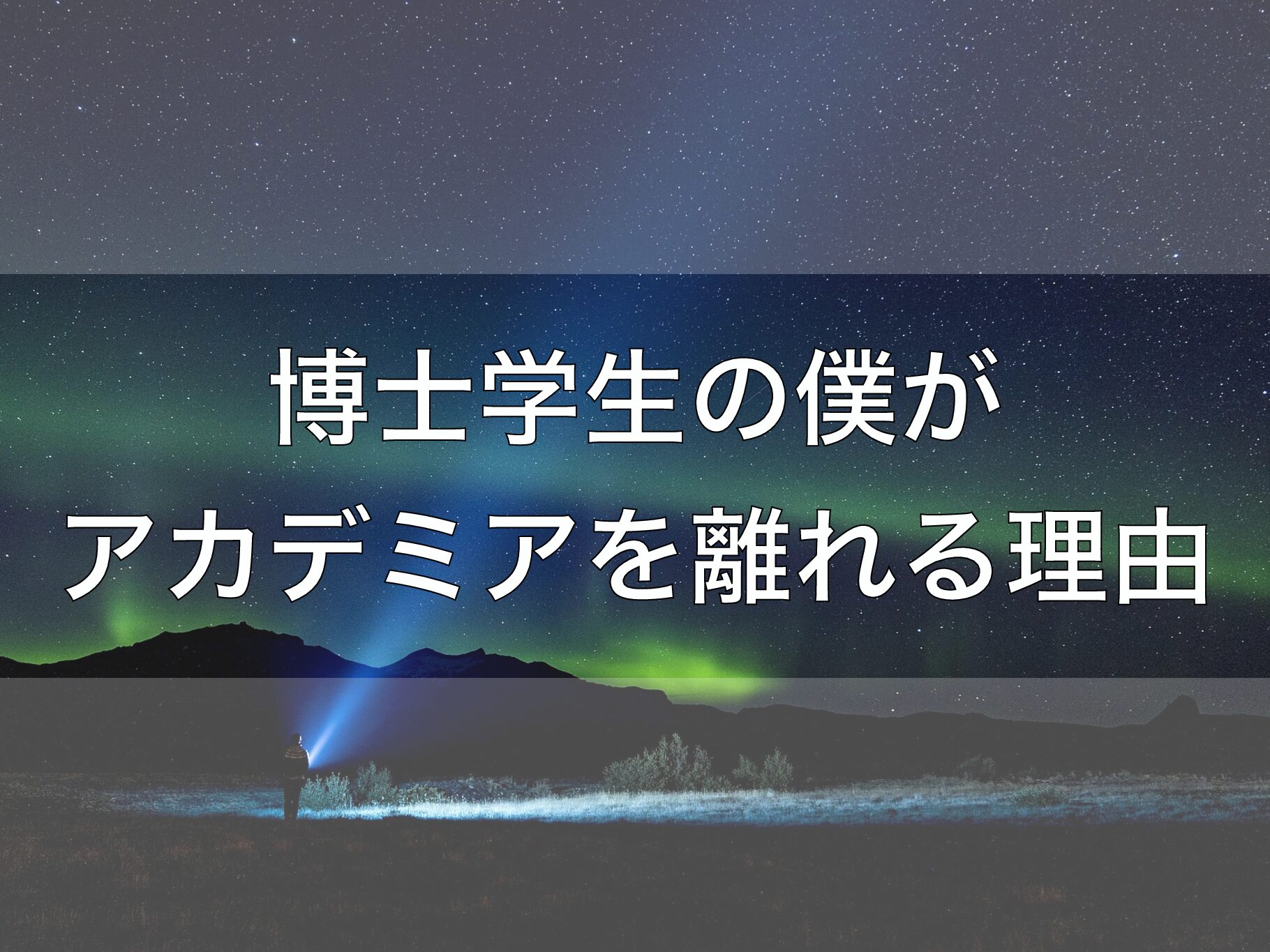

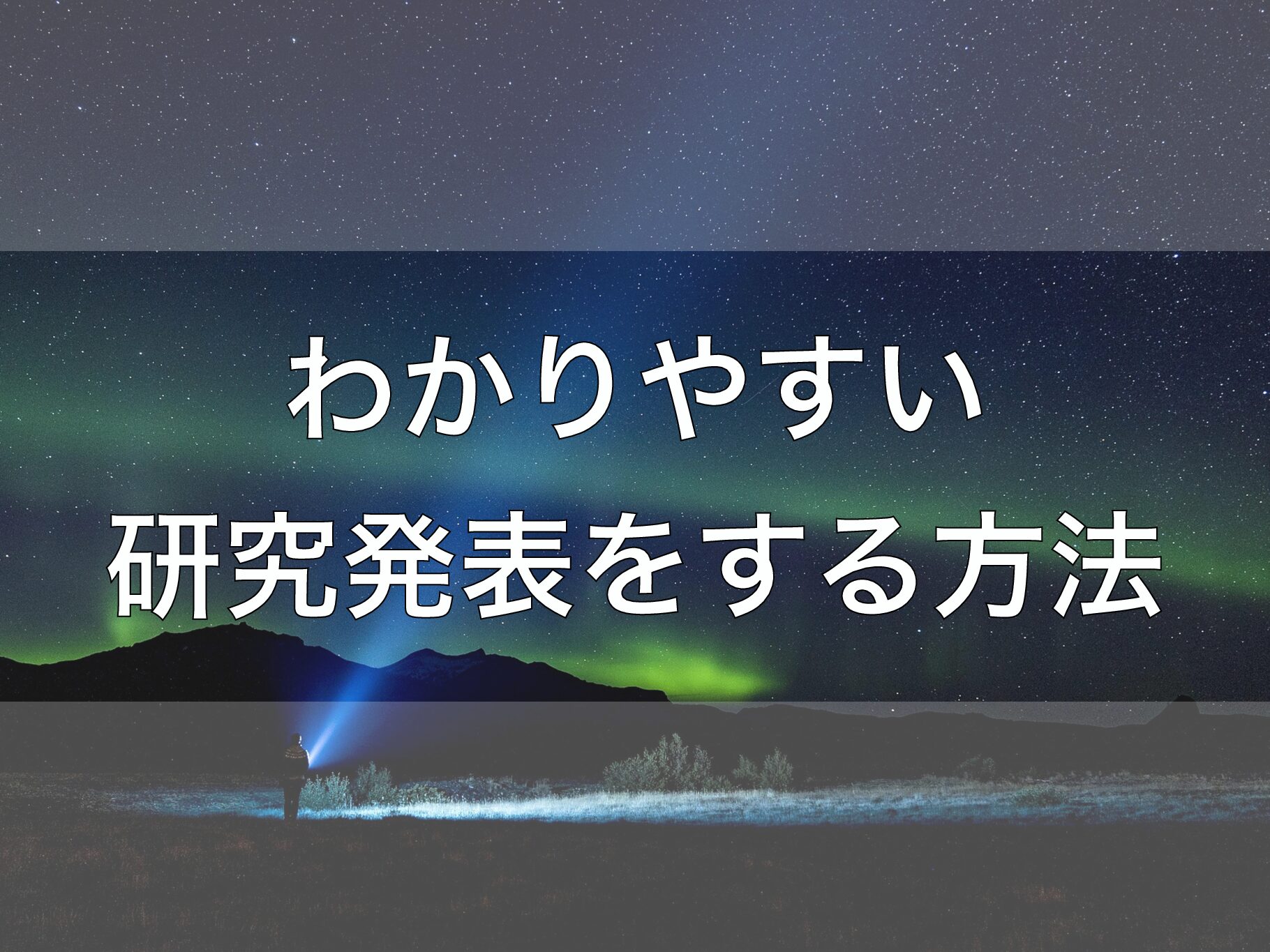

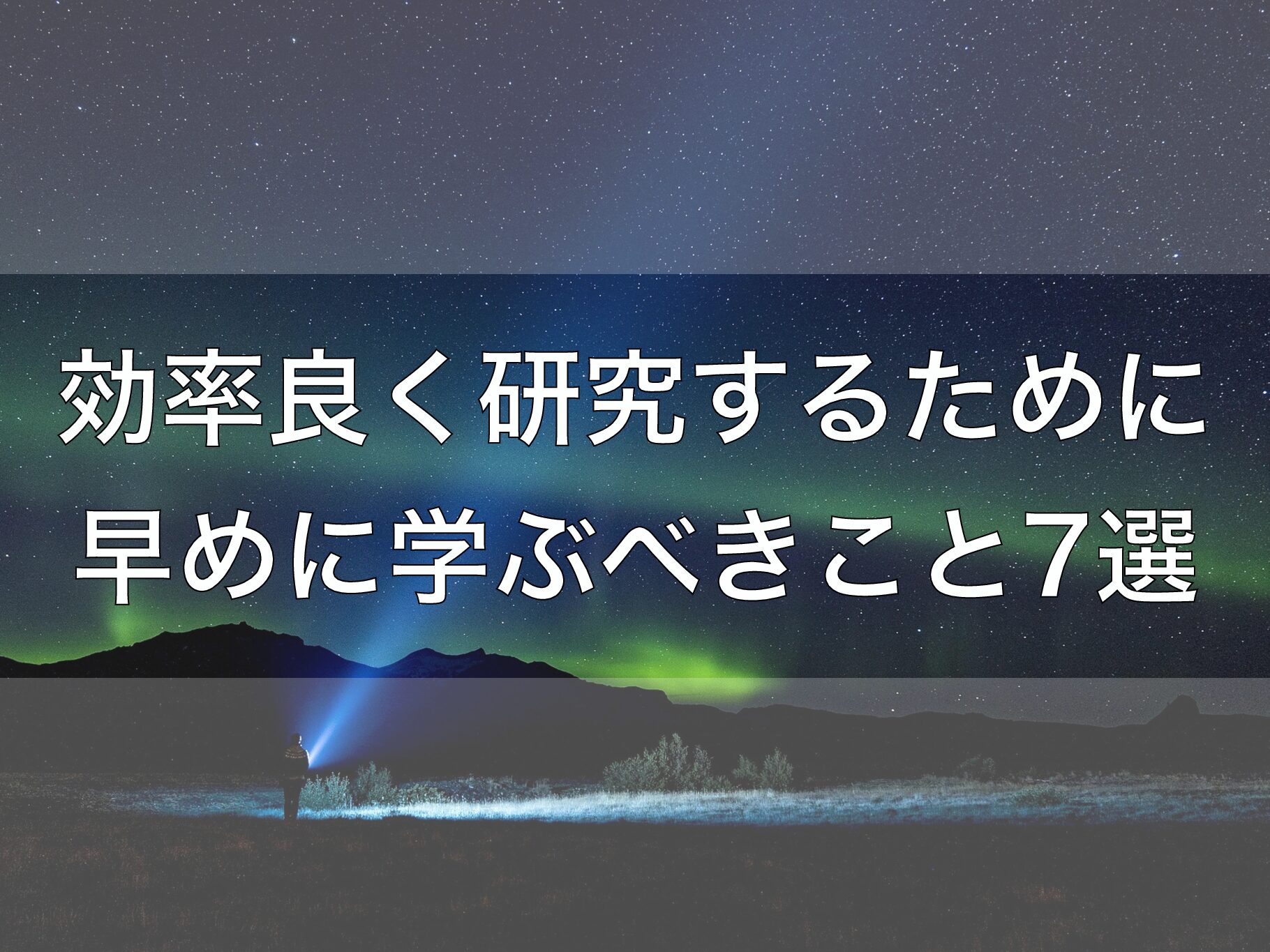
コメント